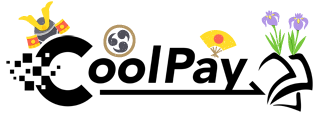2025/08/14
世界のファクタリング事情ってどんな感じ?日本と違いあるの?

クールペイです!
ファクタリングのお仕事をしている日々の中でふと思ったことがあります。
海外のファクタリングってどんな感じなんだろう⋯?
日本では怪しい存在に見られがちがファクタリング会社
ファクタリング会社に対してなんとなく懐疑的な見方をする風潮ありませんか?
私たちとしては、お客様の資金繰り改善に貢献したいと思ってるし、お客様の事業が発展して欲しいという気持ちで取り組んでいるのですけど、あまりにも斜に構えた見方をされる方が多くて時々悲しくなります⋯。
主要国におけるファクタリング事情
そんな時にふと思ったのは海外事情。
海外でのファクタリングの見られ方ってどんななんだろう?
まず、GDP比率では各国こんな感じだそうです↓

最もファクタリングの市場規模が大きい欧州は、全体のGDPに対して12.7%にもなる2700億米ドル(約40.5兆円)という規模でファクタリングが普及している。
欧州のファクタリング市場が大きい理由は、売掛金を早期に現金化するのが一般的という企業文化が定着していることに加え、2024年4月に施工された「EUの遅延支払い指令」により、支払期限を最大60日以内にしないといけない決まりができて、超過した場合は利息や罰則がかかることになりました。
これにより、仕事を受注した際に発生する材料代、原料代の支払いが前倒しされてしまうことにより、ファクタリングの需要が増加したとのこと。
また、売り手側(ファクタリング的にいえば売掛先側)も従来よりも支払いを前倒ししないといけなくなったため、リバースファクタリング(買い手が支払いを早期化する仕組み)が急増しました。
他の国々も、ファクタリングを資金繰りの潤滑油としようとするような法整備が進められており、ファクタリングを推奨する国が大半のようです。
⋯世界単位では、ファクタリングはむしろ推奨される立場にあるんだなぁ⋯とちょっとビックリでした。
日本でもファクタリングを推奨する法整備が進んでいる。
世界がファクタリングを推奨する中で、日本はどうなっているのか?
実は、日本もファクタリング市場を後押しするような法整備が進んでいます。
まず、2020年の民法改正。
債権譲渡禁止特約(例:「この売掛金は譲渡不可」)があっても、債権譲渡(ファクタリング)は有効であることが民法466条2項にて明確にされた。
これにより、売掛先が債権譲渡を禁止している場合でもファクタリング契約が有効であることになった。
それ以前は、売掛先が譲渡不可にしていた場合はファクタリング契約の有効性が微妙だったのですが、この法改正により、ファクタリング契約の有効性が認められる可能性が大幅に高まった。
更に、来年(2026年)に実施予定の手形廃止。
日本のファクタリングの普及が遅れた一因は確実に手形文化だった。手形で受け取った売掛を手形買取業者に出すことで現金化するという、ファクタリングと類似した仕組みが既に日本にはあった為、ファクタリングの需要をある程度抑えていたという事情がある。
この、手形廃止が実施されると、売掛金を現金化する方法がファクタリングに一極化する為、ファクタリングの需要は高まると思います。
今回調べてみて思ったこと⋯
ファクタリングは、まだまだこれから拡大する資金調達方法だから懐疑的に見る人が多いのかもしれない。
また、新しい業界だからこそ、色々なファクタリング会社が乱立しており、なかにはお客様とのトラブルが絶えないファクタリング会社もあるようなので、ここで悪い体験をした場合には懐疑的にならざるを得ないのかもしれない⋯。
しかし、世界的な視点でも、日本国内の視点でも、ファクタリングの需要は高まっているし、各国政府もそれを推進しているように思う。
会社経営をするうえで資金はとても大切。
その資金調達方法の一つとしてファクタリングが役立てる場面が増えたらいいな。
そして、多くの企業が飛躍するきっかけづくりができたらいいな⋯と思いました。