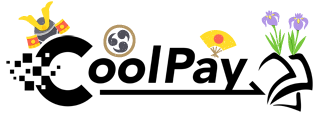2025/10/29
立て続けのレイオフは衰退か?進化か?

クールペイです!
2025年。
テック業界を震撼させるレイオフの嵐が止まりません。
この背景には、Aiやロボットの導入が進んでいることもあり、技術の進歩により業務が効率化されていることが思いつきますが、これは、いったい進化なのか、衰退なのか、、人間目線で考えてみたいと思います。
立て続けのレイオフ。160万人の雇用が消失か?
10月28日にはアマゾンが1万4千人の人員削減を発表。
更に、最大3万人の社内職を対象とした大規模カットが予定されており、これは過去最大規模とのことです。
GM(ゼネラルモーターズ)も同月、200人以上のエンジニアを解雇。
メタやマイクロソフト、スターバックス、ナイキといった大手も相次いで人員整理に踏み切っています。
レイオフ追跡サイトLayoffs.fyiによると、今年だけで216社、約9万8千人のテック従業員が職を失った。 真の数字はこれを上回る可能性が高く、585件のレイオフで17万6千5百32人が影響を受けているという恐ろしい状況です。
急激にレイオフが実施される背景にはなにがあるか?
この立て続けのレイオフは単なる一過性の調整では無いと思われます。
その背景には、複合的な経済要因が絡んでおりますが、真っ先に挙げなくてはならないのは、パンデミック後の過剰雇用。
2019年から2022年にかけ、アマゾンは従業員を倍以上に増員。
しかし、その後、需要の急減で「スリム化」が急務となりました。
加えて、米労働市場の停滞が深刻。
採用数は急減していて、レイオフ率は2020年以来の最高水準に達しているというのが現状です。
インフレの継続と成長鈍化により、経営者がコスト圧縮をせざるを得ない現実も大きく影響しています。
そして、関税引き上げや消費者支出の冷え込み、資金調達の難航も追い打ちをかけるかたち。
そして、なによりも、AIやロボットの現場導入より人手が不要になってきているという技術の進化による代償を強く求められています。
マッキンゼーの予測では、2030年までに米国の30%の仕事が自動化され、60%がAIツールで大幅に変革されるという。
ゴールドマン・サックスでも、移行期の失業率が0.5%上昇すると見込んでいて、 特に、データ入力やルーチン作業、CADエンジニアのような職種が真っ先に標的になるとみています。
そして、世界経済フォーラム(WEF)の報告書も、成長鈍化で160万人の雇用が失われると警告。
160万人が雇用を失う世界。
それは、深刻で無いわけがありません。
雇用の急減は避けられないのか?
一方で、PwCの「2025グローバルAIジョブス・バロメーター」では、AIが人を「より価値ある存在」に変えると主張しています。
自動化されやすい職種でも、生産性が向上することで、今まではなかった新たな役割が生まれるとの見方も。
2030年には、AIが1億7千万の新規雇用を創出するとの試算もあるのだとか。
その考えに基づくと、ロボットが単純労働を肩代わりすることにより、そこから生じるクリエイティブな問題解決やデータ分析の需要を爆発的に増やすという見解を強めているようです。
先程、「2030年までに米国の30%の仕事が自動化され、60%がAIツールにより大幅に変革される」というマッキンゼーの予測を紹介しましたが、一方でマッキンゼーは、企業活用による生産性向上で4兆4千億ドルの経済効果を予測しています。
つまり、雇用は「減る」ではなく「変わる」ということなのかも知れません。
将来はどうなっていくのか?
レイオフの大波によって生活に支障が出る人があふれることになるのがここからしばらくの流れで、これは避けられないように思います。
しかし、Ai、ロボットの現場採用により、新たな仕事が生まれる。
ここに勝機を見出すことができれば、雇用は増えるのかも知れません。
そして、Ai、ロボットという新たな技術をもって、人類全体はいまだかつて無いほどのスピードで文明を進化させるのかも知れません。
ある意味、今は進化の過程にある代償の時期なのかも知れません。
新しい時代がやってくるにあたって、どうしていけばよいか、真剣に考えないといけないなぁ…と思いつつ、なかなかどうして良いかわからない私です。